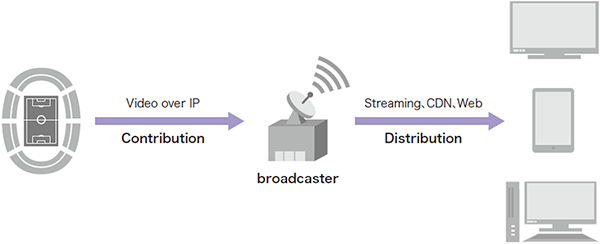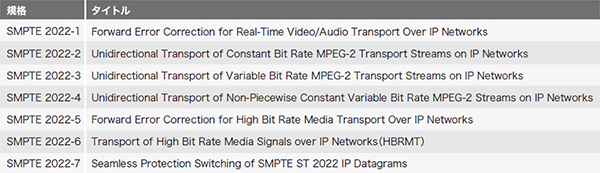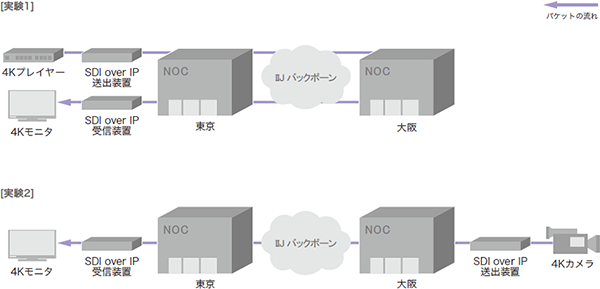ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- 目次
2. コンテンツ配信
いよいよ始まった放送機器のIP化とIIJの動き
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が5年後に近づいてきました。5年後はまだ時間がある将来に感じますが、その舞台に立ちたい競技選手にとっては1年1年が戦略になってきます。同じことはスポーツの世界だけでなく、オリンピック・パラリンピックを支えるシステムについても言うことができます。現在、実験から普及を目指している4K/8K放送はその最たるものでしょう。放送といったレガシーなシステムは、ドッグイヤーと言われているインターネットの世界とは異なり、ことを起こすには時間と調整、そしてイノベーションが必要です。今回はその放送の世界で起ころうとしている「IP化」の波について説明します(放送だけに、波が起きているわけです)。
放送の仕組み、特にスポーツ中継を例にとって図示します(図-1)。スタジアムなど(よく英語でvenueと表現されます)で開催されるイベントは、当然ながら現場で撮影・収録する必要があります。この模様を放送番組に仕立てて放送やネット中継に供するには、venueで撮影された素材を放送局に伝送する必要があります。後日放送するのであれば、カメラで撮影したメモリカードやハードディスクを持ち運びすれば良いのですが、中継となると話は別です。放送局舎内での映像編集(例えばテロップ加工)もあるため、できるだけ高い品質を保ったまま、映像を放送局へリアルタイムで伝送する必要があります。このために、放送局では様々な手法が用いられています。マイクロ波中継や衛星中継などの基地局と中継局を用意するのが一般的です。お天気カメラなどは、安価なコンシューマ用回線が用いられたりしますし、緊急の場合は携帯キャリアのデータ通信が使われることもあります。あるいは映像専用の専用線サービスを通信キャリアから購入する場合もあります。一般的には品質を確保したい場合は安定した方法で、速報性が重視される場合は機動性が重視されています。これら広い意味でのネットワーキングを、業界では"Contribution"と呼んでいます。日本語では「集信」となるでしょうか。対比して、放送局から視聴者に届けられる区間、地上波やBS、CSやOTTの部分については"Distribution"と呼ばれています。これは「配信」ですね。
図-1 放送局を中心としたContribution及びDistribution
このContributionや放送局舎内で活躍している物理メディアが「同軸ケーブル」です。皆さんのお宅にもある、アンテナからテレビを繋いでいるものです。同軸ケーブルは19世紀に発明され、高周波信号の伝送特性に秀でています。かつてEthernetでも利用されていた時代がありました(10BASE2、10BASE5)。現在でも無線や映像の世界では広く使われている技術です。放送局内部の映像伝送として古くアナログ時代から使われており、現在でもSDI(Serial Digital Interface)という規格によりフルハイビジョンの伝送に用いられています。
このように安定した、ある意味では「枯れた」技術の次を模索する動きがあります。それは放送映像の4K/8K化によるものです。これらの映像は非圧縮状態では非常に大きな量のデータになります。4Kを例に取るとフルハイビジョンの4倍のデータになります。現状では4Kの映像を同軸ケーブルで伝送しようとすると、画面を『田』の字に分割する処理をした上で、同軸ケーブルを4本使って伝送することになります。同軸ケーブルは決して軽くて扱いやすい形状ではありません。それが4本も必要となると、取り扱いの難度が高くなることは確実です。さらに同軸ケーブルでは4K/8K映像信号のような大容量データを伝送するために確保が必要な高周波特性が限界に達しているという指摘もあります。
そこで着目されているのが光ファイバーです。通信業界ではこの10年程度で急速に普及が進み、NOCやデータセンターの内部配線用、あるいはまさに"FTTH"の名前のとおり家庭へのネットワーク接続にも採用されるようになりました。電磁波の影響を受けにくいという特質を持ち、また大容量データを伝送できるパフォーマンスを持つため、放送・映像機器でも利用が進んできています。映像信号は"SDI"という規格名が示すようにデジタルデータであり、ある意味では通信との垣根は既にありません。近い将来、放送機器で伝送に用いられる物理メディアは、ファイバーに取って代わられていくことになると言われています。そして、放送・通信機器での光ファイバー採用は、上位レイヤーに更なる変更を促すことになります。これまでSDIは放送局やそのエコシステムでは絶対的な存在でしたが、いずれ放送のエコシステムはIPの上に構築されていくのではないか?とのコメントも増えてきました。2013年9月にアムステルダムで開催された国際放送機器展(IBC)で、ある企業が、「SDI must die. (死すべしSDI)」と大書したポスターを会場内に展示していたことがありました。ある意味では、業界を自己否定するようなメッセージでしたが、近い将来に台頭するであろう新時代の技術への期待感を抱いたのを覚えています。
米国で放送関係の規格を定めているのはSMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers、米国映画テレビ技術者協会)という団体です。そのSMPTEの規格に、"SDI over IP"技術の勧告が入り始めています。これは、Video Services Forumという業界団体で議論・検討がなされたものです(表-1)。
表-1 SMPTE STANDARD 2022シリーズの題名
この「SMPTE 2022」をサポートする製品は、この1年で急速に増加してきました。2015年4月にラスベガスで開催されたNAB Showや同年9月にアムステルダムで開催されたIBCでも、その勢いは増す一方です。ソニーやEvertz Microsystems(カナダ)、Grass Valley(米国)といった放送機器メーカの重鎮がこぞってSMPTE 2022の採用を進めているのは、4K/8K対応にとどまらず、IPネットワークを用いた映像伝送に可能性を感じ取り、その分野で業界をリードしたいからに他なりません。日本でもソニーをはじめメディアグローバルリンクスやPFUといった企業が、SMPTE2022のサポートを始めています。
こうした"SDI over IP"は、まずはローカルエリアから始まるでしょう。シャーシの中、ラックの中といったごく狭い範囲からはじまり、ラックを越え、フロアをまたぐという、いわゆるローカルエリアネットワークの形をしたSDI over IPネットワークが形成されるのではないかと、筆者は考えています。なぜならIPネットワークが代替する同軸ケーブルのネットワークがそうした範囲で形成されているからです。
しかし、IPネットワークのポテンシャルは「インターネットワーキング」にこそあります。オフィスネットワークやキャンパスネットワークも、ある一定以上の規模になると複数の相互接続されたネットワークから構成されているはずです。多数の組織や目的があった場合、ネットワークを分割することで使用形態を明確にし、利便性を失うことなく接続する。まったく同じことが、映像ネットワークでも言えるはずです。そして「リモートネットワーキング」もIPネットワークの大きな利点です。遠隔地もローカルエリアと相互接続性を持つ。インターネットがその代表例ですが、映像ネットワークでも大きな可能性が広がることは言うまでもありません。
4K非圧縮映像をIPネットワークで伝送するのは、そう簡単なことではありません。13Gbpsというと、10ギガビットイーサネット回線が2本必要になってしまいます。そこで、圧縮技術が登場することになります。現在欧米でポピュラーなのがJPEG 2000(J2K)という圧縮形式です。非可逆圧縮形式ですが、"visually lossless" (見た目のロスなし)を800Mbps程度で達成できると言われています。帯域で1Gbpsを切ることができれば、4KのIP伝送は現実味を帯びてきます。10ギガビットイーサネット回線2本ともなると多大なるコスト出費に迫られますが、1ギガビットイーサネット回線であれば低コストのネットワーク機器を用いて、安価なサービスを複数選ぶことができるようになるからです。
IPネットワークの可能性は、既にお天気カメラの伝送や携帯網を使った現場中継で示されています。これまで高価、あるいは限定的だった遠隔地からの中継が簡単に実現できるようになるのです。実際、お天気カメラなどはカジュアルな装置として普及しています。SIerが大掛かりなシステムを提案するのではなく、既に世の中に広まっているパーツを組み合わせて使う。まさにインターネット的な考え方です。こうした考え方が成功し続けてきたことが、放送機器のIP化に向けたダイナミックな動きに繋がってきたと、筆者は考えます。
放送機器メーカの観点では、IP化に伴って自らの指針に選択を迫られていると言えます。これまで蓄積してきたSDIの技術とは別に、光ファイバー、そしてIPという新しい技術に取り込む必要があるからです。IPは放送機器の根幹部分に入り込んでいくだけに、どのように取り込むべきなのか悩ましいところではないでしょうか。放送機器では、IPの世界とは別の「ルータ」と呼ばれる機器が存在します。字義どおり、映像のソースとディスティネーションのペアを決定する役割を持ちますが、この映像ルーティングの機能をIPスイッチ機器の上位に構築しなければなりません。アプリケーションレイヤーとトランスポートレイヤー、双方への深い知識が要求されることになります。
アグレッシブなのはカナダのEvertz Microsystems社です。彼らは数年前から"Software Defined Video Network(SDVN)"というコンセプトを提唱し、自ら、機器へのIP技術実装を進めています。もじりではありますが、まさに自分たちのためのSDNを作り上げているのです。筆者はこの点に興味を覚え、Evertz Microsystems社のSDVN担当エンジニアにインタビューしたことがあります。もともと、映像系のエンジニアリングをしていたが、2010年頃から社の方針でEthernetやIP技術の獲得を始めたと語ってくれました。彼らには、IP及び映像レイヤーを垂直横断的に設計・実装できる強みがあると、筆者は考えています。
一方、2015年のNAB ShowでGrass Valley社はネットワーク業界の雄、Cisco Systems社とのパートナーリングをアピールしていました。また、Juniper Networks社やArista Networks社などとも連携するというメーカが多くありました。もはやコモディティとなったIPネットワーク機器を、カジュアルに使えるようになるのが一番良い。自社でIP技術の開発をするより、多機能・大量生産されている機器と組み合わせられるようにするのが好ましい、ということでしょう。これはこれで慧眼と言えるでしょう。なにより、IPネットワークに対する考え方が合理的です。
1点考えなければならないことは、これらIPネットワーク機器メーカと放送機器メーカそれぞれが考えているIPネットワークというものに齟齬が生じていないかということです。IPネットワークは汎用的であるが故に繁栄してきました。メールもWebもストリーミングも、すべて同じIPネットワーク機器で扱うことができます。一方、放送機器メーカが想定するのは、極端に言えば「放送事故の起きないIPネットワーク」です。ここには大きな開きがあります。IPネットワークでは冗長性を確保するために、ルーティングプロトコルが用いられています。途中の経路で回線断があったとしても、自動的に切り替えや迂回させることができます。例えばWebの閲覧やビデオチャットなどでは切り替えがあったとしても気づかないことがほとんどでしょうが、秒間60フレームをコンスタントに送り続けるようなSDI over IPの世界で、果たしてその切り替えが受け入れられるでしょうか。
放送業界では、よく「A系/B系」というアクティブ-アクティブの構成が取られています。これをSDI over IPに適用すると、JPEG2000の4K映像を、A系回線・B系回線パラレルに送出し、受け側ではどちらかの信号を採用するという形になります。最もクリティカルな用途であれば、そのような構成にならざるを得ません。しかし、この「A系/B系」は設備投資が倍になるというデメリットもあります。もう少しIPネットワークのカジュアルさを活かした構成は作れないものだろうか。ネットワークの良いところとSDI over IPは、果たしてどこで折り合いをつけるべきなのでしょうか。
もちろん目的志向で作成されているIPネットワークも存在します。その一例が、ナノ秒のレベルでネット取引を成立させるためのトレーディングネットワークでしょう。このような非常に高いレベルの要求に応えるIPネットワークが構築できるかどうか、ポイントになるのはIPネットワーク機器メーカ、そして私たちのようなネットワークサービスプロバイダの回答にかかってくると考えています。
そこでIIJではSMPTE2022による商用サービスを目指し、SDI over IPの実証実験を開始しました。もちろん、使用する回線は自社バックボーンです。他のお客様のトラフィックが既に乗っているバックボーンに、こうした映像系の、しかもミッションクリティカルなトラフィックを多重してみる。専用線ではないため、このトラフィックが特別扱いされるわけではありません。そこで、帯域的に空きがある区間で実証してみることにしました(図-2)。
図-2 IIJバックボーンを利用したSDI over IP実験
どちらも映像の入出力としては4K60pです。ですが、メーカによって符号化が異なります。これは圧縮及び伸張に要する所要時間をどこまでペナルティとして考えるか、という開発側の思想の違いです。いずれにせよ非常に短い時間(フレーム数)に収まるような遅延でしかありませんが、放送用途においては「早ければ早い程良い」ということになります(では最低要求がどの線なのか、は難しい問題です。感覚によるところもままあるのが、放送業界における技術要求です)。
実験1は、IIJバックボーン上に仮想的にLayer 2 Networkを構築し、東京から大阪を経由し東京へ戻ってくる経路を設定しました。アプリケーションから見るとプライベート網に見えますが、トラフィックそのものはIIJバックボーン上に多重されています。実際には送出機器も受信機器も同じ場所に設置されたのですが、ネットワークだけ遠隔地(大阪)を経由してきていることになります。3.5Gbpsという非常に大容量のデータとなりますが、まったく問題なく伝送することができました。ネットワークの遅延は当然あるのですが(23ms程度)、送出側映像プレイヤーから受信側モニタまでの総合遅延は、見かけ上1フレームに収まっていました。4Kでは秒間のコマ数が60フレーム(厳密には59.94フレーム)あり、時間に換算すると1フレームが16.7msとなります。33.4msの間にEnd-to-Endの伝送が完了しているわけで、低遅延を狙ったパフォーマンスが発揮できたことになります。システムが設計どおりの動作をしているとはいえ、この結果には単純に驚きました。
実験2は、全区間にインターネット網を使用したことが特色です。産学協同プロジェクトであるサイバー関西プロジェクト(CKP)の協力を得て、送出機材を大阪に設置しました。CKP内部のネットワークを通り、IIJのバックボーンを大阪から東京へと経由したのち、IIJオフィスで4K映像を出力しました。これらの通信は、グローバルIPv4アドレスを用いて行われました。実際には軽微なパケットロスが観察されましたが、技術的には問題なくカバーできることが確認できています。
今後、SDI over IPの波は技術的に加速することになると思います。しかし、エコシステムが整備されるのはこれからです。放送局が慣れ親しんだ信頼性のある技術を捨て、新たな技術を獲得しようとするとき、求められることはなんでしょうか?これだけインターネットが普及し、放送局もその存在をむしろ活用しようとしている今、Contribution-Distributionをどのように整備すれば良いのでしょうか。そこでは、インターネットの世界でIP技術を育て普及し運用してきた私たちのナレッジが必ず役立つと信じています。

執筆者プロフィール
山本 文治 (やまもと ぶんじ)
IIJ プロダクト本部プロダクト推進部企画業務課 シニアエンジニア。
1995年にIIJメディアコミュニケーションズに入社。
2005年よりIIJに勤務。主にストリーミング技術開発に従事。同技術を議論するStreams-JP Mailing Listを主催するなど、市場の発展に貢献。
ページの終わりです