ページの先頭です
- ページ内移動用のリンクです
- ホーム
- IIJについて
- 情報発信
- 広報誌(IIJ.news)
- IIJ.news Vol.192 February 2026
- IoTはAIで戦略資産へ――産業の現場を変える次世代データ活用の真価
IoTで足場固め IoTはAIで戦略資産へ――産業の現場を変える次世代データ活用の真価
IIJ.news Vol.192 February 2026

産業の現場に変革をもたらすには、どんなデータ活用が必要なのか?
この課題を念頭に、本稿では、まずIoTの現状・課題を整理したうえで、戦略的な“IoT × AI”活用について考察する。
IoTNEWS代表 株式会社アールジーン 代表取締役
小泉 耕二 氏
1973年生まれ。フジテレビ Live News αなどメディア出演・DX教育活動を行なう。YouTube「小泉耕二のデジタイド」でも発信。大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどコンサルティングファームを経て、現職。
IoTの「第2の進化」が始まった
産業分野におけるIoTの風景は、この10年で一変しました。製造業では設備の稼働状況がモニタリングされ、物流業ではトラックの位置情報がリアルタイムに追跡されるようになり、建設現場では作業員や重機の動きがデータとして記録されるようになりました。
かつては「現場は経験で回すもの」とも言われてきました。しかし、IoTの導入により、経験の裏側にある現象がデータによって可視化され、「意外なところで工程が詰まっていた」「離れた場所からでも現場の状況を正確に把握できる」といった新しい発見が生まれました。
意思決定も感覚だけに頼らず、データで裏付けられるようになりつつあります。さらに、センサ、ネットワーク、クラウドといった技術要素はこの数年で急速に発展し、コモディティ化しました。高性能なセンサが廉価になり、通信も高速・低遅延が当たり前となり、クラウドの利用も特別なことではなくなりました。その結果、IoTを導入すること自体、もはやむずかしいチャレンジではない状況になったと言えます。
では、IoTはすでにやり尽くされたのでしょうか? 答えは「No」です。むしろ今、IoTは「第2の進化」の入り口に立っていると言えます。
コモディティ化は終わりではなく新たなスタートライン
技術がコモディティ化すると、一般には「どの会社でも同じことができる」ようになります。そして、技術そのものを差別化要素にしづらくなります。これは、IoTも例外ではありません。
実際、センサ・通信・クラウドの3点セットを売りにしているベンダは多く、ある程度の“見える化”だけ実現したいのであれば、短期間でかたちにできるようになりました。しかし、AI時代のIoTは、ここからが本番です。
IoTが真価を発揮するのは、「データが集められるようになったその先」において「どうデータを構造化し、AIが学びやすいかたちで蓄積するか」という設計に踏み込んだ時なのです。
例えば、同じ振動データ、温度データでも――
- どの頻度で取得しているか
- 他のどんな情報と一緒に扱っているか
- 異常値やノイズをどう処理しているか
によって、AIが抽出できる洞察の質は大きく変わります。言い換えれば、IoTを構成する技術そのものがコモディティ化されたとしても、データの設計思想と蓄積の仕方には、まだまだ大きな差別化の余地が残されているのです。
IoT × AIが実現する「自律した現場」
では、IoTとAIが融合する時、現場の姿はどう変わるのでしょうか。これをひと言で表すと、「自律的に学習し、日々アップデートされる現場」となります。
まず1つ目の変化は「現場が自分で自分を説明できるようになる」ことです。従来のデジタルツインは、人がモデルを作り、そこにデータを当てこむというものでした。しかし今後は、設備データや作業動線、人やモノの滞留時間、生産能力のゆらぎといったデータをAIが組み合わせ、文脈として昇華してくれるようになります。その結果、「今現場がどういう状態にあるのか」が、リアルタイムに推定可能になるのです。「今日、このライン構成なら、ここがボトルネックになりそうだ」「この順序で工程を組み換えれば、 ◯%生産能力を上げられる」といった提案を、毎日のようにAIが行なうようになります。「昨日と同じやり方を再現する」のではなく、「最適な現場の姿が日々更新される」のです。
2つ目の変化は「AIが現場のコンディションを理解するようになる」ことです。設備の音の微妙な違い、作業者の動きのテンポ、フォークリフトと人の流れのバランス……など、これまで熟練者の“勘”でしか捉えられなかった「空気感」を、AIは時系列データとして記録・学習・推論します。すると「今朝のラインはいつもよりわずかにテンポが遅い」「この作業者は疲労が蓄積しつつある」「このままだと午後、倉庫内のこのエリアに渋滞が起きそうだ」といった微妙なズレを先回りして教えてくれるのです。単に故障を予知するのではなく、現場のコンディションをマネジメントしてくれるAIが登場しつつあると言えます。
3つ目は「AIが現場の制約条件を理解し、全体最適をリアルタイムに提示してくれるようになる」ことです。設備のキャパシティ、作業員の数とスキル、材料の到着タイミング、天候、納期、安全ルール……など、さまざまな条件の組み合わせをもとに人間の頭のなかだけで判断を下すのは、あまりに複雑で困難です。一方、AIは過去のデータから「こういう条件下では、どこで遅延が起きやすいか」「どの作業順序ならロスを生みにくいか」といった文脈を学習できます。その結果、「ここを30分、後ろ倒しにすれば、全体の遅延を最小化できる」「今日は雨なので、この順番で資材を投入したほうがいい」など、現場全体を見渡した最適解を出せるようになるのです。
建設現場のように毎回条件が変わり、過去の経験をそのまま流用しづらいケースでも、複数の現場データを学習したAIであれば、「この地形なら、この工程でリスクが高まりそう」「このパターンは過去に遅延が発生した現場と似ている」といった示唆を与えてくれます。こういったAIの活用によって、経験の浅い担当者でも、熟練者に近い判断が下せるようになるのです。

食品工場に見る「文脈を読むAI」の実力
ここで具体的なイメージとして、パン工場の例を共有したいと思います。発酵室の温度・湿度を管理し、生地の状態を一定に保つ――これらはすでに多くのパン工場で実現されていますが、現場の悩みはその先にあります。同じレシピ・製法で作っているのに、焼き色やふくらみが微妙に違う、ロスが多い日がある……それらの原因をなかなか説明できないのです。
そこで、AIを活用するわけですが、まず目を向けるべきは、発酵温度や湿度といった単独のデータではありません。生地に焼き色が入るまでどのくらい待たされたか、材料投入のテンポはいつもと違わなかったか、粉や酵母のロットはどうか……これら1つ1つはわずかなゆらぎでしかありません。AIはそれらを組み合わせて、品質との相関を探ります。すると「このロットの粉の工程は、発酵時間を少し短くしたほうがいい」「この作業者の時は生地の滞留時間が長くなりがちだから、ラインの前後を調整したほうがいい」といった、熟練工がやっていた微調整をデータとして説明してくれるのです。
AIは単に温度や時間を監視するだけでなく、現場で起きていること、つまり「文脈」を学習して、熟練工の経験値を再現・拡張する存在へと進化していくのです。
技術中心のIoTからビジネス価値中心のIoTへ
ここまでの話は、あくまで現場の目線から見たIoT × AIでした。ここからは、どうやって「戦略的なIoT × AI活用」に引き上げていけばいいかについて解説します。
ポイントは、現場の課題を現場の言葉で終わらせないで、「経営課題の言葉」に翻訳することです。例えば「人に依存した判断を減らしたい」という現場の課題は、「属人化した判断への依存を減らすことで、事業の再現性を高め、スケールしていきたい」という経営課題に変えられます。また「品質のばらつきを抑えたい」という現場の課題は、「品質のばらつきによるクレーム対応、廃棄コスト、再加工コストが利益を圧迫しているので改善したい」という経営課題に変えられます。さらに「業務全体を最適化したい」という現場の課題は、「全体最適を実現することで、需要変動への対応力を強化し、機会損失や無駄なコストを減らしたい」という経営課題に変えられます。
つまり、経営レベルにまで引き上げることで、初めて「IoT × AI」の投資は「現場改善」だけでなく「経営戦略の一部」として位置付けられるのです。そうなると、必要とされるデータも変わってきます。現場のデータはもちろん、財務データ、他部署のコスト、営業や保守に関するデータなども必要になるでしょう。どんなデータを、どのくらいの粒度で集めて、どんな文脈としてAIに学習させるのか?
このように“逆算”することが、IoTを「コスト」ではなく、「戦略的な投資」に変える第一歩になるのです。
データ設計はもはやIT部門の仕事ではない
ここまで見てきたような世界を実現するには、1つだけ重要な前提条件があります。それは、AI活用を前提とした「データ設計」が行なわれていることです。
どのくらいの粒度でデータを集めて、どの情報同士を結びつければ「文脈」となるのか、何を正常とし、何を異常とするのか、将来、他の工場や部門のデータと連携することになった時、無理なくつながる構造になっているか……こういった「設計」は、もはやIT部門だけに委ねるべきテーマではありません。現場を熟知した人、経営課題を理解している人、そしてITやデータを扱える人が、同じテーブルについて議論すべきことなのです。
スモールスタートであっても構いません。重要なのは「将来、AIが学びやすいかたちでデータを残しておく」という意識なのです。その意識が、5年後、10年後に競争力の差となって確実に現れるでしょう。

IoTはAIとともに産業のOSへ
最後にポイントをもう一度整理すると、これからのIoTは「単にデータを集めるための仕組みではない」ということです。
現場の状態を観測し、AIがデータと文脈に意味を与え、日々のオペレーションを学習し、未来の姿を予測していく――この一連の循環が企業に定着した時、IoTは現場を支えるインフラから「企業の骨格を形作る産業OS」へと進化します。
IoTが現場を写し、AIがそれを解釈・推論する。その結果、現場そのものが自律的に変化する。この新しいサイクルこそが、産業IoTの未来であり、企業が手に入れるべき次世代の戦略資産なのです。
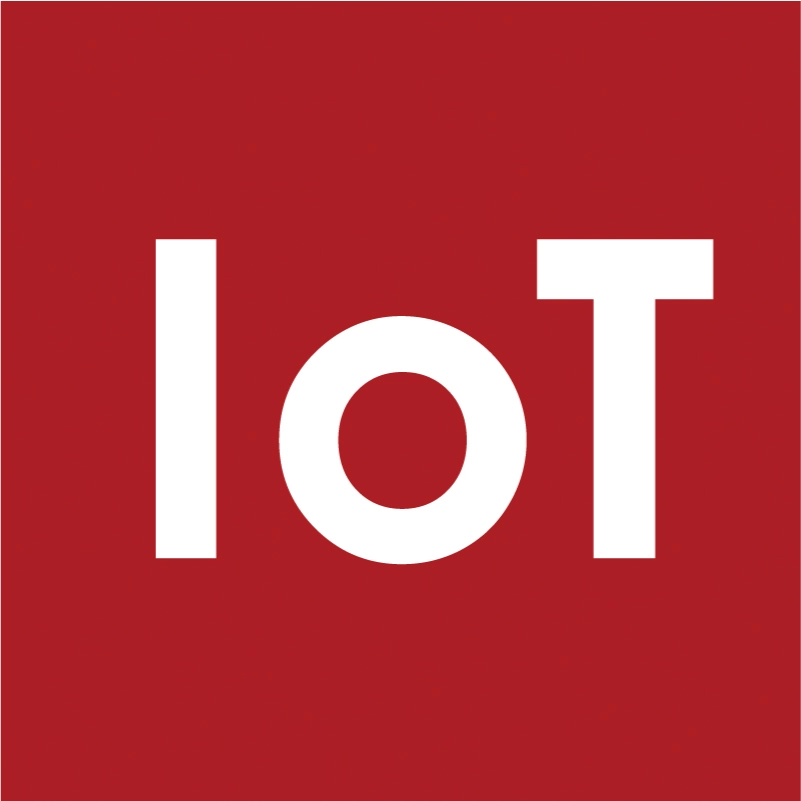
- 企業情報
- 情報発信
- バックボーンネットワーク
- 採用情報
ページの終わりです