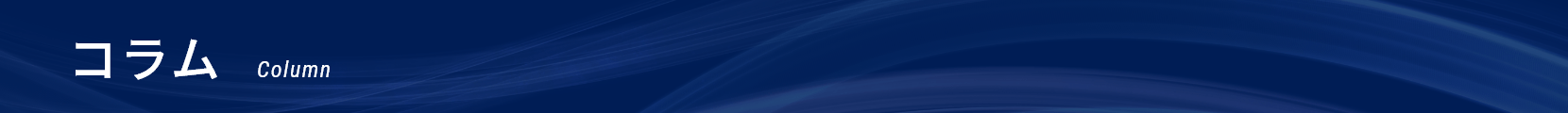
海外進出の"失敗の本質"
【座談会】ASEANにおける日本企業のグローバルマネージメント
2015/09/18
IIJのグローバル戦略は今年で3年目に入り、世界の主要4極(ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、上海)にクラウド設備の設置を完了した。特に東南アジアでは、インドネシアにもジョイントベンチャーを設立し、積極的なサービス展開を進めている。
今回は、ベストセラー『失敗の本質』の著者の一人である寺本氏をはじめ、ASEANに精通した識者にお集まりいただき、過去の海外進出における“失敗の本質”を探り、今後の課題を解決する方策について語っていただいた。

左から:丸山 孝一、毛利 正人氏、寺本 義也氏、穂高 弥生子氏、清水 博(司会進行)
清水:
中国経済がやや減速し、ASEANが"チャイナプラスワン"の投資先として注目されるなか、今年の12月にはASEAN経済共同体(AEC)が発足します。日本企業にとってASEANはどんな重要性を持っているでしょうか?
寺本:
ASEANの重要性はふたつあると思います。市場としての重要性と、生産拠点としての重要性です。まず市場のほうですが、ASEANは経済成長性のスピードが非常に速く、人口も直近の数字で6億5,000万に達し、大きな需要が見込まれます。次に生産拠点ですが、ASEANの労働力は(シンガポールを除けば)総体的に低廉かつ豊富で、域内における産業集積も進んでいます。
最近ではASEAN10(テン)とも呼ばれ"チャイナプラステン"という見方も可能です。よって、日本・ASEAN・中国のトライアングルは三者それぞれのメリットにしていかなくてはならず、今後、東アジアでは新たな関係構築が進むと考えられます。
毛利:
日本企業の国際的な拠点再編の動きを見ますと、中国は拠点の移管元として増加しており、"チャイナプラスワン"の流れを裏付ける調査結果が出ています。もちろん日本にとって中国市場の重要性は今後も変わりませんが、生産拠点としては、人件費など生産コストのアップでASEANに比べると魅力が薄くなってきています。加えて、種々の機能が中国に集中するリスクを日本企業は心配しているようです。こうした動きと相まって、ベトナム・タイ・インドネシアなどが新たな拠点の移管先として上位にランクされています。
穂高:
私は"2013"がキーポイントだったと考えています。この年、海外からASEANに流入する投資額が史上最高になり、中国への投資額を抜きました。同じ年、日本からASEANへの投資額も中国に対する額を上回って、一気に2倍以上になりました。
ASEAN投資の特徴は、リターン・オン・インベストメントが高い、つまり"儲かっている"ということです。数字で言いますと、日本からASEANへの投資残高はグローバルの15パーセント程度ですが、日系の製造業では経常利益の約35パーセントがASEANから生み出されています。
玉虫色のインドネシア
清水:
インドネシアは訪問のたびに、経済発展を実感する反面、ネガティブリストの存在など進出のむずかしさが指摘されています。皆さまは、インドネシアをどのようにご覧になっていますか?
穂高:
通常、ネガティブリストは外資に徐々に開放されていくのですが、インドネシア政府が行なった2014年の改正では重要な自由化は行なわれず、逆に規制が強化された部分もありました。これに対し、外国の投資家は一様に落胆し、新聞には「New Negative List is truly negative」という見出しが出ました。先日、私どものジャカルタ・オフィスの弁護士が「インドネシアはバランスを重視する国だから、ひとつオープンしたら、別のところをクローズするのだ」と説明していましたが(笑)。
丸山:
インドネシアは市場のポテンシャルが非常に高く、ITインフラに対する需要は日本企業だけでなく、現地企業からも寄せられています。IIJは同国への進出に際して、現地パートナーと組んだほうがいいとの判断から合弁会社を設立しました。我々同様、インドネシアに関心を持つ日本企業は、どのようにリスクを軽減して進出すべきか、いろいろ苦慮していると思います。
毛利:
コンプライアンスリスクに関してですが、トランスペアレンシー・インターナショナルというNGOが調査を行なっていまして、インドネシアはASEANのなかでも腐敗認識指数が悪いほうの国です。よって、日本企業も汚職が絡むコンプライアンスリスクには十分な注意が必要です。
寺本:
インドネシアのポジティブな面は、ASEANの四割を超える人口を抱えるうえに平均年齢が若く、市場および生産拠点として非常に有望なことです。加えて、天然資源が豊富です。さらに、対日関係が良好で、日本に対する国民感情も悪いところがない。インドネシアに対するODAは日本が最大の援助国で、日本からの援助もインドネシアが最大です。
ネガティブリストもたくさんありますが、ロングスパンで考えると、ポジティブな側面を非常に多く持っている。経済は多少のデコボコがあっても今後も確実な成長が見込めるし、外資規制も徐々に緩和されていくと思います。
海外進出の"失敗の本質"
清水:
ここからは、ASEANもしくは海外に進出している日本企業の課題を掘り下げて、対策を考えたいと思います。穂高先生はM&Aなどに携わる機会も多いでしょうが、日本企業が陥りやすい失敗の事例をあげていただけますか。
穂高:
時間的な制約からか、買ったあとの統合のことまで熟慮しないでM&Aを行なうケースも多いとの印象を受けます。
毛利:
買うこと自体が目的になっているケースも多いようです。
寺本:
M&Aを行なうときの日本企業の問題は、戦略が明確でない点です。「売り物がありますよ」と言われたからデューデリジェンスを始めるみたいに……。自社の戦略のフレームワークにその案件が入っているか否かをジャッジしないといけないですね。
穂高:
最初に統合後の青写真をはっきり持たないままに、最小限の費用、最小限のデューデリジェンスだけでとにかくM&Aを実行してしまう。そして数年後、だんだん中身がわかって問題が表面化する。その段階になって、インドネシアでは買収をし、タイでは自前で立ち上げ、といったふうに、これまで全体を考えずにばらばらに築いてきた拠点をどうやって統合・管理していくのかということが改めて問題になり、「どうにかしたいのだけど」というご相談がこのところ増えている感じがします。
海外進出で、特にさほど規模が大きくない場合だと、コストをかけたくないという意識が強く働くと思いますが、受けられると思っていた税制上の優遇措置が実は受けられないことが判明したり、許可を得ているライセンスとは別の事業に手を出して、本業のライセンスまで失効してしまうとか、数年後に発覚する問題は重大である場合も少なくありません。
丸山:
M&Aの場合、時間的な制約もありますし、欧米と違ってアジアの企業はドキュメントも英語でなかったりするので、課題が多いですね。
清水:
デューデリの甘さはしばしば問題視されます。また、PMI(Post MergerIntegration)も、ポイントがズレていることが多いですね。
寺本:
PMIは本来なら、あと(Post)から実施するのではなく、買うか否かを判断するプロセスに織り込んでいないといけない。先ほど予算をケチるという話が出ましたが、情報や知識、つまり"見えないもの・形のないもの"にはお金を払いたがらないという風潮は今でもあるように感じますね。
毛利:
私もデューデリジェンスは大変重要だと考えています。ビジネスやフィナンシャルのデューデリは一般的ですが、リスクやコンプライアンスの点からもデューデリをやるべきです。もちろん買う前の段階だと精査できる資料も時間も限られていますが、事前にやっておくことでPMIもスムーズにいくと思います。
海外子会社のマネージメントの苦労
清水:
毛利先生は、ご著書のなかで海外子会社の経営失敗のパターンについて述べられていますが、おもな要因はどこにあるのでしょうか?
毛利:
日本企業の海外子会社が上手くいかないケースは二通りに大別できます。ひとつは、子会社の上層部が本社から派遣された駐在員でかためられているケースです。これはオーガニックに育った会社に多いのですが、現地に即した経営・人材活用ができていない。もうひとつは、M&A後も経営者を続投させた際などによく見られるケースです。本社コーポレート部門との意思疎通が十分でなく、事実上、放任経営に陥っています。この場合、本社は業績(数字)は見ていても、コンプライアンスリスクなどが放置され、あとから大きな問題に発展する危険性があります。
清水:
今のお話を聞くと、即座に「ガバナンスを強化する」ということになりそうですが……。
毛利:
海外の子会社で不祥事が起こるたびに、ガバナンスを強化するといったコメントが繰り返されてきました。ガバナンスを効かせる際、日本人は現地に乗り込んでマイクロ・マネージメントを行なおうとする傾向にありますが、原理原則を明示したうえで、現地の裁量に委ね、結果をモニターするというやり方は苦手かもしれませんね。
対応策として、人材を日本から派遣するのは、立ち上げのときや緊急時には有効です。ただ、将来的・長期的に現地のニーズを取り込むことを考えると、ディシジョンも現地を優先すべきでしょう。そのためには、本社による動機付けや原理原則を明らかにして、その枠のなかで自由にやれるようにするのが第一歩です。当然、汚職に関しては、本社が「絶対にダメだ」とハッキリ言うべきです。
寺本:
子会社に対するガバナンスはまだ見える範囲に入りますが、孫会社あたりに潜在的なリスクが隠れていて、甚大な被害につながるケースも想定されます。
毛利:
大型M&Aの場合、買った会社に多くの子会社・孫会社が存在するケースがあります。その場合、親会社(本社)が子会社を飛ばして孫会社の面倒を直接みるのは、子会社のモラル・ハザードが起きるので避けるべきで、親が子を、子が孫をみるようにすべきだ、というのが私の考えです。
寺本:
企業経営にとって大切なのは、経験——特に失敗の経験を組織で共有することです。総じて日本人は重要な意思決定に際して、そこに関わる人数が多い。明らかに多すぎる。その結果、責任の所在が曖昧になり、個人を超えたかたちで経験が蓄積されないのです。
欧米企業も失敗しますし、失敗するのが組織だとも言える。大事なのは「失敗から何を学ぶか」です。3M(スリーエム)という米国企業がありますが、そこでは「躓くのは歩いている証拠」と言われているそうです。イノベーションは失敗を伴うもので、失敗から学ぶことが進歩につながる、という意味です。
ASEANの新潮流
清水:
日本企業がASEANの統括拠点を強化・再編する動きが見られますが、どのように進めるべきでしょうか?
穂高:
多くの企業がASEANの統括拠点をシンガポールに置いていますが、十分に機能していなかったり、単なる持株会社に過ぎなかったりします。シンガポールの統括会社には税制の優遇措置などの各種メリットが用意されていますが、これを享受するための基準を満たすビジネス実体をシンガポールに置ける会社とそうでない会社がある。
近年、タイがシンガポールの競合として名乗りをあげています。タイはメコン地域の中央に位置し、周辺国と面でつながっているのでボーダレスになりやすい。単一の生産拠点や市場が成熟しており、そのぶん賃金もあがっていますが、単純な作業・生産はラオスやカンボジアなどに移したりしています。そしてタイは今年の年頭、外資の優遇措置のポリシーを全面的に見直して、製造業からハイテク産業にターゲットを切り替えました。同じような動きは、マレーシアやフィリピンでも出始めています。
現在、シンガポールに統括会社としての実態がないのであれば、他国の活用も検討すべきですし、やはりシンガポールのメリットを活かしたいというのなら、思い切って事業の相当部分を移転するか、または、財務と事業の拠点を分けるデュアル・リージョナルヘッドクォーターという考え方もあります。
毛利:
ある外資系企業の話では「直接レポートする部下は7名まで」にしているそうです。それ以上になると上司の管理スパンを超えてしまうということです。そういう意味で考えると、日本企業はASEAN地域に第二本社のような拠点を設けて、本社の管理スパンを整理する必要があると思います。
しかし同時に、地域統括会社があるために、かえって業務が混乱しているケースも見られ、それらの多くは統括会社の存在意義の曖昧さに起因しています。当然、事業に関する意思決定は現場ベースで行なったほうが良く、これはディセントラリゼーションになります。一方、コンプライアンスやセキュリティといった管理面は本社の情報発信力が重要で、セントラリゼーションが望ましいと考えます。
丸山:
AECの"統合"と言いますが、むしろ競争が激しくなるのでは、という声をよく聞きます。ITに関しても、複数の国が「自分たちがハブになる」と名乗りをあげています。
寺本:
実際、その通りでしょうね。AECの仕組みはベースラインを共通化し、人・モノ・金の流通を自由化・活発化することを狙っています。
統括拠点の話にも関連しますが、グローバルな成長戦略には、文字通りグローバルな戦略と、マルチドメスティックな戦略の二種類があります。前者は世界中で統一した戦略を用い、後者はローカルに特化した戦略を用います。そして昨今では、企業理念などは前者、個々のビジネスは後者といった具合に、両戦略のハイブリッド化が主流です。その利点は、イノベーションを促進できるところです。イノベーションとは既存の知識・技術の新しい組み合わせですが、これを高度化させるには、ドメスティックな環境で得た経験をグローバルに活用・共有していくハイブリッド化が有効なのです。これからの地域統括拠点には、そのハブとしての役割が求められるでしょう。
多様性を勝ち抜く
清水:
AECの展開も注視しながら、グローバル・マーケットで勝ち残るために日本企業は何をすべきでしょうか?
穂高:
AECは2015年設立を目指してきましたが、100パーセントのスタートは望めない状況です。ただ、今年中には今後五年間の新たな目標設定が出ると思われ、2020年あたりにはほぼ完成するだろうと見られています。そして、そこに至る段階で、国別の役割分担が明確になっていくのではないでしょうか。
AECの目標は、単一の市場と生産拠点の確立とされていますが、ASEAN各国の多様性は残っていくし、それを残しつつ共同体を築いていくのがAECの本意だと思います。日本企業にとって、この多様性への対応はむずかしい反面、「リスクを分散できる」とも考えられる。つまり「この国がダメでも、他の国は同じ歩調をとるとは限らない」ということです。そう考えると、ASEAN特有の事情もプラスに転化できると思います。
毛利:
ASEAN市場は、日本以外にも欧米・中国・地元企業が入り乱れて、競争が激しくなり、ビジネスには迅速な意思決定が求められます。その際——これは私見になりますが、日本企業には"内なるグローバル化"が必要だと感じています。グローバル企業を標榜しながら、日本本社は旧態依然としたスタイルで運営している会社が多いように思います。今後、カギになるのは多様性=ダイバーシティであり、海外との人的交流や社外取締役などを通して、外の目をもっと入れるべきではないでしょうか。
寺本:
まず、日本企業は進出先の国や地域に根ざした社会貢献を積極的に行なうべきです。それが進出先で受け容れてもらえる基盤になる。資金の供与も大切ですが、雇用を増やして賃金を支払うことや、品質の高い商品・サービスを提供することも立派な社会貢献です。
あとひとつは、ビジネスの消耗戦を回避することです。日本国内の消耗戦を国外にまで持ち出すようでは、進出先もハッピーになれません。それを避けるには、独自性を打ち出すことが一番です。戦略とは「価値のある違い」を生み出すことであって、同じモノなら安いほうが選ばれて、結局、消耗戦になる。先ほど話したイノベーションの本質は、新しい価値を提供することであり、ひいてはそれが最良の社会貢献につながると思います。
丸山:
ASEANは多様性を尊重しながらも、AECとして一体化を目指している。そのなかで我々が考えなければならないのは、地域の特性に合ったイノベーションを起こし、サービスを差別化しながら社会に貢献していく、そして地域に根ざすことで、また次のイノベーションを生んでいく"生"のサイクルとそれを実現するための戦略です。そのためには、まず我々自身が国際化しなければならないと感じています。
清水:
今日は大変貴重なお話をありがとうございました。

寺本 義也(てらもと よしや)
1965 年、早稲田大学第一政治経済学部卒業。67 年、早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了。同年、富士通入社。72 年、早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了。81 年、明治学院大学経済学部教授。89 年、筑波大学大学院教授。94 年、北海道大学経済学部教授。98 年、北陸先端科学技術大学院大学教授。2000 年、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授。10 年、経営研究所所長。著書・共著に『失敗の本質』『ネットワークパワー』『パワーミドル』『学習する組織』『技術経営の挑戦』『戦略の本質』『東南アジアにおける日系企業の現地法人マネジメント』『国家経営の本質』など。

毛利 正人(もうり まさと)
米国公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人。クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社代表取締役社長。早稲田大学政治経済学部卒業。米国ジョージワシントン大学修士課程修了。国内大手企業、国際機関(在ワシントンDC)、大手監査法人のエンタープライズリスクサービス部門ディレクターを経て現職。日本企業の海外子会社に対するコーポレートガバナンスサービスを専門としており、世界各地で内部監査、リスクマネージメント、買収海外子会社の調査、コーポレートガバナンス体制導入といったプロジェクトを多数実施。著書に『図解 海外子会社マネジメント入門』など。

穂高 弥生子(ほだか やえこ)
弁護士。おもに企業買収・再編を含む企業法務、会社訴訟その他の紛争案件の分野に約20 年の経験を有する。ベーカー&マッケンジー東京オフィスのコーポレートM&A グループ、ASEAN フォーカスチームに所属。ベーカー&マッケンジーの他のASEAN 域内オフィスとともに、ASEAN 経済共同体の発足に伴い日本企業が活用できる施策や、域内のビジネス再構築について助言を行なうほか、この分野について各種の講演、執筆を行なう。1988 年、慶應義塾大学法学部卒業。98 年ニューヨーク大学ロースクールLL.M. 取得。2004 年ジュネーブ国際大学MBA 取得。





